6歳にとっての読み聞かせの意味とは?
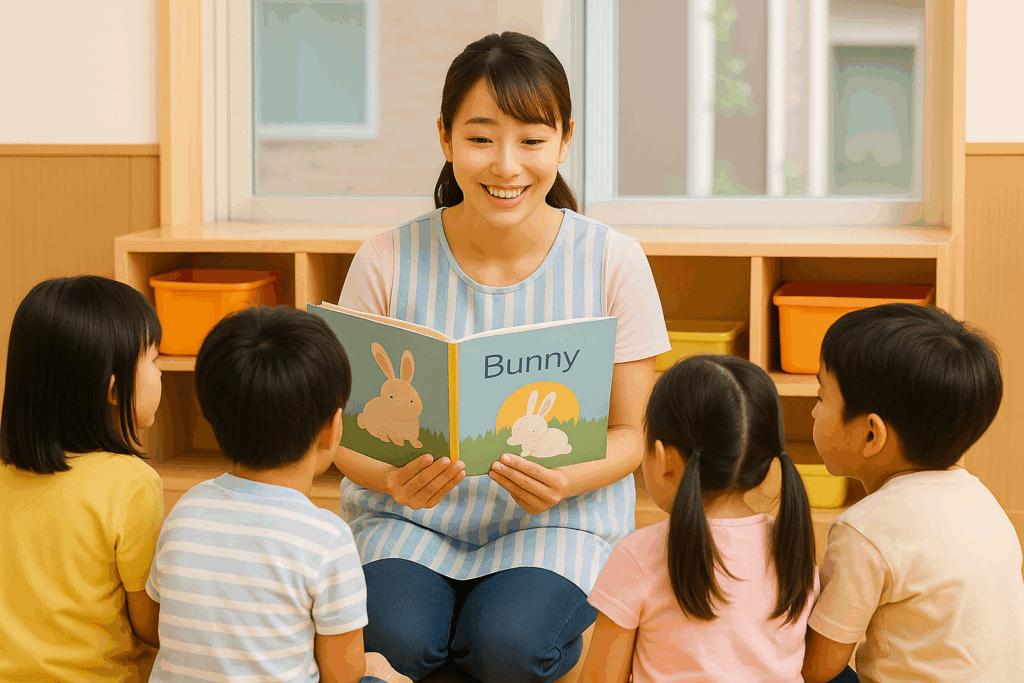
6歳といえば、自分で文字を読み始める子も多くなる時期。ひらがなやカタカナの読み書きができるようになり、「もう読み聞かせは卒業かな?」と考える保護者の方もいらっしゃるかもしれません。ですが実は、6歳だからこそ、読み聞かせがより深く心に響く時期でもあるのです。
自分で読める年齢でも読み聞かせが大切な理由
たしかに、6歳になると簡単な絵本や児童書をひとりで読むことができるようになります。しかし、自分で読むのと、大人の声で聞くのとでは得られる体験がまったく異なります。
大人が読んであげることで、言葉の抑揚・登場人物の感情・場面の雰囲気など、文字だけでは伝わりにくい「物語の奥行き」が立体的に伝わります。また、読み聞かせは子どもにとって「安心できる親子時間」でもあり、心を落ち着けて物語の世界に入り込む貴重な機会となります。
想像力・語彙力・表現力を育てる読み聞かせの効果
6歳児は、物語を通して「もし自分だったらどうするか」「これはどういう意味か」と頭の中で考える力=想像力がぐんと伸びていく時期です。読み聞かせによって、日常では出会えない言葉や表現にも触れることで、語彙力や言語表現力が自然と豊かになります。
また、読み手が登場人物になりきって感情を込めることで、感情表現の幅やコミュニケーション能力にも良い影響を与えます。これは将来、作文や人との対話の力にもつながる大きな基盤となります。
心の成長と感情理解を深める絵本の力
6歳は、少しずつ「他者の気持ちを想像する力」=共感性が芽生えてくる時期です。喜びや悲しみ、怒りや不安など、さまざまな感情を物語の登場人物を通して追体験することが、子どもの心の成長に深く関わってきます。 特に、ちょっと切ない話や複雑な感情を描いた絵本は、6歳だからこそ理解しはじめられるようになります。そうした絵本に触れることで、子どもは「気持ちっていろいろあるんだ」「相手にも理由があるんだ」と、感情理解の幅を広げていくことができるのです。
6歳児におすすめの絵本の選び方

6歳になると、子どもの読書経験も徐々に広がり始めます。自分で本を読む力が育ってくる一方で、大人が選んで読み聞かせる絵本には、「心の成長を支える」という大きな役割があります。この時期にふさわしい絵本を選ぶためには、子どもの発達段階や興味に合ったテーマや表現を意識することが大切です。
登場人物の気持ちに共感できるストーリーを選ぶ
6歳児は、「主人公の気持ち」や「相手の気持ち」に少しずつ関心を持てるようになります。そのため、心情の変化が丁寧に描かれている物語がおすすめです。たとえば、誰かとケンカをしてしまった話や、困っている人を助ける話など、自分の生活と重ね合わせられるテーマがあると、より深い共感を得られます。
感情に寄り添う絵本は、相手の立場で考える力=思いやりを育てる第一歩にもなります。
長めの文章でも興味を引く構成・テーマとは
6歳は集中力が伸び、物語の筋を追えるようになる時期です。そのため、少し長めの文章や起承転結のあるストーリー展開でも、興味を引く内容であれば最後まで夢中になって聞いてくれます。
おすすめは、冒険やファンタジー、ちょっとした謎解きが含まれているような絵本です。「どうなるんだろう?」「続きを知りたい!」というワクワク感が、物語への興味を高め、読書への意欲にもつながっていきます。
自立心・社会性・好奇心を刺激するジャンル別絵本選び
6歳は、小学校入学を控えたり、新しい友達関係が生まれるなど、社会との関わりが一気に広がる年齢です。そこでおすすめなのが、以下のようなテーマを扱った絵本です。
- 自立心を育てる絵本:「ひとりでできた」「失敗しても大丈夫」などの前向きなメッセージが込められた作品。
- 友だち関係を描いた絵本:協力・対立・仲直りといった社会性を育むストーリー。
- 好奇心を刺激する絵本:科学・自然・歴史などへの興味を引き出す知識系絵本も◎。
ジャンルの幅を広げることで、子どもの世界観や思考の幅もどんどん豊かになっていきます。
読み聞かせにおすすめ!6歳向け絵本5選
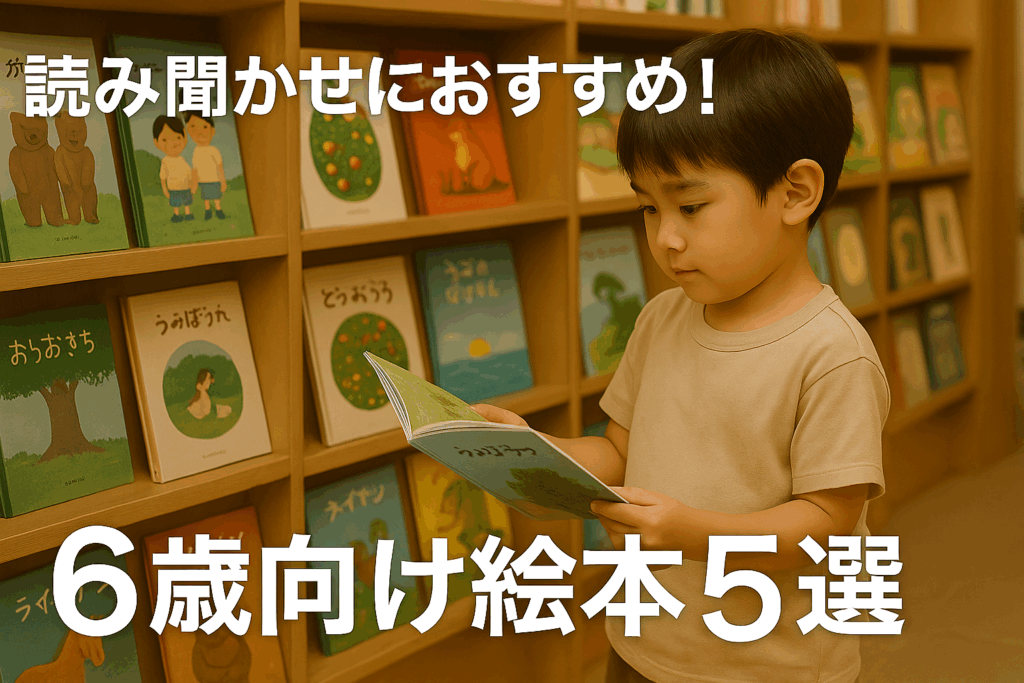
6歳児には、物語の奥深さやキャラクターの心情をしっかり受け止められる力が育ってきます。この時期に出会う絵本は“読む”という行為以上に、心に残る体験として深く印象に残ります。ここでは、読み聞かせにぴったりの名作絵本を5冊ご紹介します。
深いメッセージが心に残る「100万回生きたねこ」
(作・絵:佐野洋子/講談社)
何度も生き返った「ねこ」が、初めて“誰かのために生きる”ことを知る物語。命・愛・喪失といった深いテーマを、子どもなりの視点で受け止められる一冊です。6歳ごろになると、登場人物の気持ちや変化を理解できるようになり、読み聞かせの時間が静かな感動に包まれるでしょう。
自分ってなんだろう?に答える「ぼくはあるいた まっすぐ まっすぐ」
(作:マーガレット・ワイズ・ブラウン/絵:林明子/ペンギン社)
おばあちゃんの家に向かって、ひたすらまっすぐ歩く“ぼく”の冒険を描いたシンプルで詩的な絵本。自分の意思で歩む強さやまっすぐな気持ちがストレートに伝わり、6歳の子どもの中にある「やってみたい」「一人でやりたい」という思いに響きます。
笑いとひねりが楽しい「ともだちや」シリーズ
(作:内田麟太郎/絵:降矢なな/偕成社)
キツネが“ともだち”を売るというユニークな発想から始まるシリーズ絵本。軽快なセリフまわしや個性的なキャラクターたちに、子どもたちも夢中になること間違いなし。友情とは?本当のともだちって?という問いを、楽しく・自然に考えさせてくれる名作です。
命や自然のつながりを描いた「スイミー」
(作・絵:レオ・レオニ/訳:谷川俊太郎/好学社)
小さな魚・スイミーが仲間と協力して大きな魚に立ち向かう物語。集団の中での役割・知恵・勇気といったテーマを、美しい海の世界とともに描いています。読み聞かせを通して、ひとりではできないことも力を合わせればできるという学びが自然と身につく一冊です。
想像力を広げる海外の名作「エルマーのぼうけん」
(作:ルース・スタイルス・ガネット/訳:わたなべしげお/福音館書店)
冒険好きな少年・エルマーが、りゅうの子どもを助けるために無人島へ旅立つお話。物語は少し長めですが、次はどうなるの?と引き込まれる展開と工夫が満載。6歳児の集中力と想像力を刺激し、「読み聞かせ」から「物語を楽しむ」世界へのステップアップにもおすすめの一冊です。
6歳児との読み聞かせをもっと楽しくするコツ

6歳になると、物語の内容だけでなく「読み方」や「共有する時間」そのものが、子どもにとって大きな意味を持つようになります。読み聞かせは単なる読み上げではなく、子どもの心を動かし、親子で物語を旅するような体験です。ここでは、6歳の子どもと読み聞かせをもっと楽しむための工夫を紹介します。
感情をこめた読み方で物語の世界に引き込む
6歳の子どもは、登場人物の感情や状況を理解できるようになるため、読み手の感情表現が物語の理解を助ける重要な要素になります。
声のトーンを変えたり、間を取ったりすることで、キャラクターの気持ちや場面の雰囲気がぐっと伝わります。ときにはオーバーに演じてみたり、笑いながら読むことで、子どもが「絵本の世界に入り込む」きっかけにもなります。
読み終えたあとに「どう思った?」と対話してみよう
読み聞かせのあとは、ただ「おしまい」ではなく、感想を共有する時間をつくってみましょう。
「どのシーンが好きだった?」「このとき、主人公はどんな気持ちだったと思う?」など、子どもなりの解釈や感じたことを自由に話せるような質問を投げかけることで、思考力や表現力が育ちます。また、大人の感じ方と子どもの視点の違いを知ることができるのも、読み聞かせの大きな醍醐味です。
寝る前だけじゃない!日常の中の読み聞かせタイム活用術
読み聞かせ=寝かしつけ、というイメージが強いかもしれませんが、6歳児にはさまざまなタイミングでの読み聞かせが効果的です。たとえば、
- 朝食後の5分間読書タイム
- お出かけ前の待ち時間
- 雨の日のゆったりタイム
など、1日1回でも“絵本に触れる時間”を自然に生活の中に組み込むことで、子どもは絵本をもっと身近に感じ、読書習慣の基盤にもなります。
まとめ|読み聞かせは「読む」から「心を通わせる」時間へ
6歳は、感受性や思考力、そして社会性が大きく伸びる大切な時期です。そんな時期だからこそ、絵本の読み聞かせは「ことばを届ける」だけでなく、「心と心をつなぐ時間」として、より豊かな意味を持ち始めます。
自分で読めるようになっても、大人の声で聞く物語には安心感や発見、共感がたくさん詰まっています。絵本の世界を一緒に旅し、感想を語り合う体験は、子どもの感性や表現力を育て、親子の絆をより深めてくれるでしょう。
「絵本 読み聞かせ 6歳」という言葉に込められた時間は、今だけのかけがえのない成長の瞬間です。ぜひ、日常の中に読み聞かせのひとときを取り入れてみてください。

コメント