七夕を絵本で楽しもう|季節行事の魅力を伝える読み聞かせ

七夕はどんな行事?子どもにわかりやすく伝えるポイント
七夕は、年に一度だけ織姫と彦星が天の川を渡って会えるというロマンチックな伝説がもとになった日本の伝統行事です。保育園では「短冊にお願い事を書く日」として親しまれていますが、子どもたちに伝えるには難しい部分もあります。
そんなときに活躍するのが絵本。色鮮やかなイラストややさしい語り口で、七夕の由来や意味を自然と理解できるようになります。文章だけでは伝わりにくい星や天の川のイメージも、絵本なら一目でわかり、子どもたちの想像力を大きく刺激します。
絵本で伝える「おりひめとひこぼし」の物語
七夕の由来とされる「織姫と彦星」のお話は、実はとても奥深く、愛情や努力、時間の大切さなど、多くのメッセージが込められています。
物語を題材にした絵本では、織姫と彦星の出会いや別れ、年に一度の再会をやさしいタッチで描いており、小さな子どもでも感情移入しやすくなっています。中には動物や妖精が登場するアレンジバージョンもあり、親しみやすさと理解しやすさが魅力です。
夜空を見上げると「あれが彦星かな?」と実際の星に興味を持つきっかけにもなり、絵本を通して自然や宇宙への関心も育まれます。
年齢別に選ぼう!絵本が教えてくれる七夕の楽しさ
絵本選びのポイントは、子どもの年齢と発達に合った内容かどうかです。
- 0〜2歳児には、短くて繰り返しのあるリズム感のある絵本や、イラスト中心で理解しやすいものがおすすめ。七夕飾りやお星さまが大きく描かれていると視覚的に楽しめます。
- 3〜4歳児には、物語が少し入っている絵本を選ぶとよいでしょう。織姫と彦星の話に触れながら、七夕行事の意味を少しずつ理解し始める時期です。
- 5歳以上になると、ストーリー性の高い絵本や、日本の伝承としての七夕に触れる絵本がおすすめです。お話を聞いて自分なりに感想を言ったり、質問が出たりすることもあります。
それぞれの発達段階に合わせて絵本を選ぶことで、七夕という行事が「覚えるもの」ではなく「感じるもの」として心に残るでしょう。
保育園で人気!七夕にぴったりのおすすめ絵本5選
導入にぴったり:行事の意味がわかる絵本
行事を知る第一歩としておすすめなのが、七夕の意味や流れをやさしく紹介してくれる絵本です。
『たなばたプールびらき』(福音館書店)
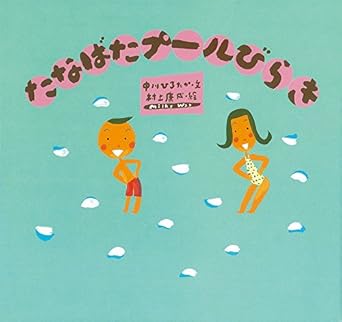
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/71kLwAkLRxL._SY342_.jpg
七夕とプール開きが重なるユニークな設定で、季節感を楽しく伝えてくれます。物語を通して「たなばたって楽しい!」という気持ちを自然と引き出してくれます。
『たなばたバス』(鈴木出版)
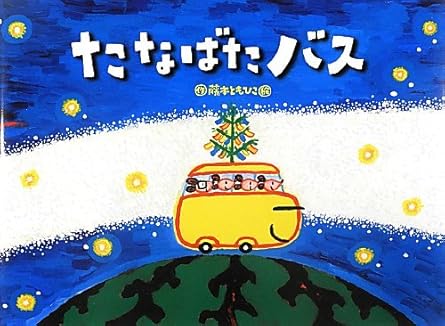
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/51q3mFNXJ6L._SX445_.jpg
七夕の日に動物たちが願いを込めてバスに乗るというファンタジー仕立ての絵本。願い事をすることの意味や楽しさが伝わりやすいです。
ファンタジー要素で夢が広がるストーリー絵本
子どもたちはお星さまや天の川といった世界観にワクワクするもの。ファンタジー要素のある絵本は、そんな気持ちをさらに広げてくれます。
『たなばたものがたり』(教育画劇)

引用:https://m.media-amazon.com/images/I/81-LfMbn38L._SX445_.jpg
オリジナルの織姫と彦星の物語を感情豊かに描いており、年長児にぴったり。星のきらめきや空の広がりが、イラストからも伝わってきます。
『おほしさま、かいて!』(講談社)
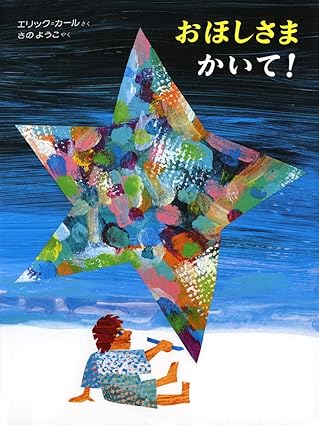
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/71tmIN-ZgNL._SY425_.jpg
絵描きの主人公が空に星を描くお話。発想の豊かさが光り、七夕の創造的な一面を感じさせてくれる一冊です。
絵やしかけが楽しい!参加型の七夕絵本
体験型・しかけ絵本も七夕にはおすすめです。
『たなばたセブン』(岩崎書店)
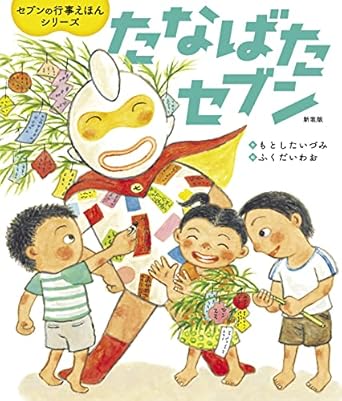
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/81MPmf8lQqL._SY385_.jpg
スーパーヒーロー「たなばたセブン」が願いごとを叶えるために大活躍する絵本で、読み聞かせにぴったり。
読み手と子どもが一緒に「セブーン!」と声を出すことで盛り上がり、保育園でのグループ読み聞かせでも大人気です。
読み聞かせをもっと楽しくするコツ

七夕にぴったりな語りかけのポイント
読み聞かせでは、ストーリーだけでなく語りかけも大切です。
七夕の絵本では、
- 「お願いごと、何にしようか?」
- 「織姫と彦星、どんな気持ちだったかな?」
- 「この星、どんな名前だと思う?」
など、想像を広げる問いかけを取り入れると、子どもたちの心により深く残ります。
保育士・保護者におすすめ!読み聞かせの工夫
読み聞かせの工夫として、以下のポイントを意識してみましょう。
- 照明を少し落として、絵本の世界観に入り込みやすくする
- 星の飾りやライトを用意して、空間演出を取り入れる
- BGMに静かな音楽を流すことで、落ち着いてお話に集中できる雰囲気づくり
特に七夕は「夜空」「星」「願いごと」といった静かなイメージがあるため、やさしい読み方や空間演出が相性抜群です。
親子で楽しむ夜の読み聞かせ|星空を見ながら読む絵本
七夕の夜、親子で絵本を読みながら外の空を眺めるのも素敵な体験です。
例えば絵本を読んだあとに、「おりひめ星(ベガ)」や「ひこぼし(アルタイル)」を一緒に探してみるのもおすすめ。
スマホアプリなどを使えば簡単に見つけることができ、絵本の世界と現実がつながる瞬間になります。
まとめ|七夕を絵本で心に残る思い出に
行事×絵本の力で感性を育む
七夕という行事は、ただ短冊を書いて笹に飾るだけではなく、「星に願いを託す」日本ならではの文化的背景や感情の豊かさを体験できる機会でもあります。
そこに絵本を組み合わせることで、子どもたちはより深く世界を「感じる」ことができます。
たとえば、
- 夜空を描いたページを見て「ほんとうにこんなに星があるのかな?」と想像をふくらませたり、
- 織姫と彦星の気持ちに共感して「1年に1回ってさみしいね」と感情を言葉にしたり、
このように、絵本があることで「行事=体験」が「行事=感情の学び」へと広がるのです。
保育園では、行事前後に同じ絵本を2回読むことで、理解の深まりや変化する子どもの反応を楽しむことも可能です。
年齢や成長に合わせた絵本選びを大切に
同じ「七夕絵本」と言っても、年齢や個々の成長によって感じ方・理解の深さは大きく異なります。
たとえば、
- 0〜2歳児は「おほしさま」「きらきら」といった音の響きや色のコントラストに反応するため、視覚的なインパクトのある絵本が喜ばれます。
- 3〜4歳児には、「どうして会えなくなっちゃったの?」などのストーリー性に少しずつ関心を持ち始める時期。わかりやすい織姫と彦星の物語を取り入れることで、物語の中に入り込む力が育ちます。
- 5歳以上の年長児になると、「登場人物の気持ちを想像してみよう」「自分だったらどんな願いごとを書く?」といった対話型の読み聞かせも楽しめるようになります。
絵本は「年齢×今のその子の感性」に寄り添って選ぶことが大切です。
保育士や保護者がその子に合った一冊を見つけてあげることは、まさに心の栄養を届ける行為だと言えるでしょう。
家庭でも保育園でも「読み聞かせ」の時間を宝物に
忙しい毎日の中で、ほんの5〜10分でも「絵本を読む時間」を持つことは、子どもとの心のつながりを深める大切な時間です。
保育園では朝の会や帰りの会、活動の切り替え時に絵本を取り入れることで、子どもたちが気持ちを落ち着けたり、空想の世界に入ったりと、心の調律ができます。
一方、家庭でも七夕の夜に部屋の明かりを少し落として、
- 「この星が彦星かな?」
- 「どんなお願いごとをしようか?」
と語り合いながら読むことで、親子だけの特別な七夕体験になります。星空アプリや手作りの天の川ライトを用意して演出するのもおすすめです。
また、読み終わったあとに「じゃあ短冊書いてみようか」と自然に活動へつなげることで、絵本→体験→思い出という経験をしてみてはいかがでしょうか。

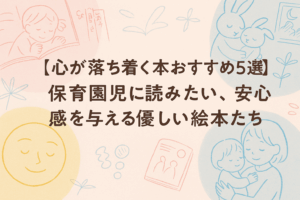
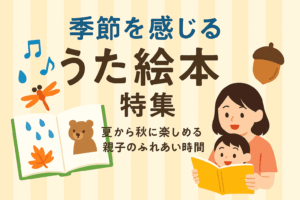
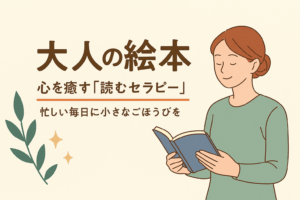




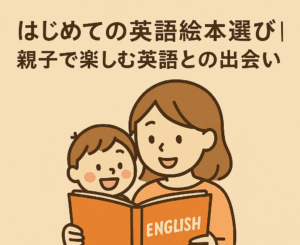
コメント