暑い夏、室内での過ごし方が増える保育園の中で、絵本は子どもたちの想像力や感性を育てる大切な時間です。特に「夏」をテーマにした絵本は、季節の自然や行事、感覚を言葉や絵で楽しむことができ、保育士にとっても子どもとの関わりを深めるツールとなります。この記事では、「絵本 夏」をキーワードに、夏にぴったりな絵本の紹介と選び方のポイント、読み聞かせの工夫まで、保育士目線で詳しくお届けします。
なぜ夏に「絵本」が効果的なのか?
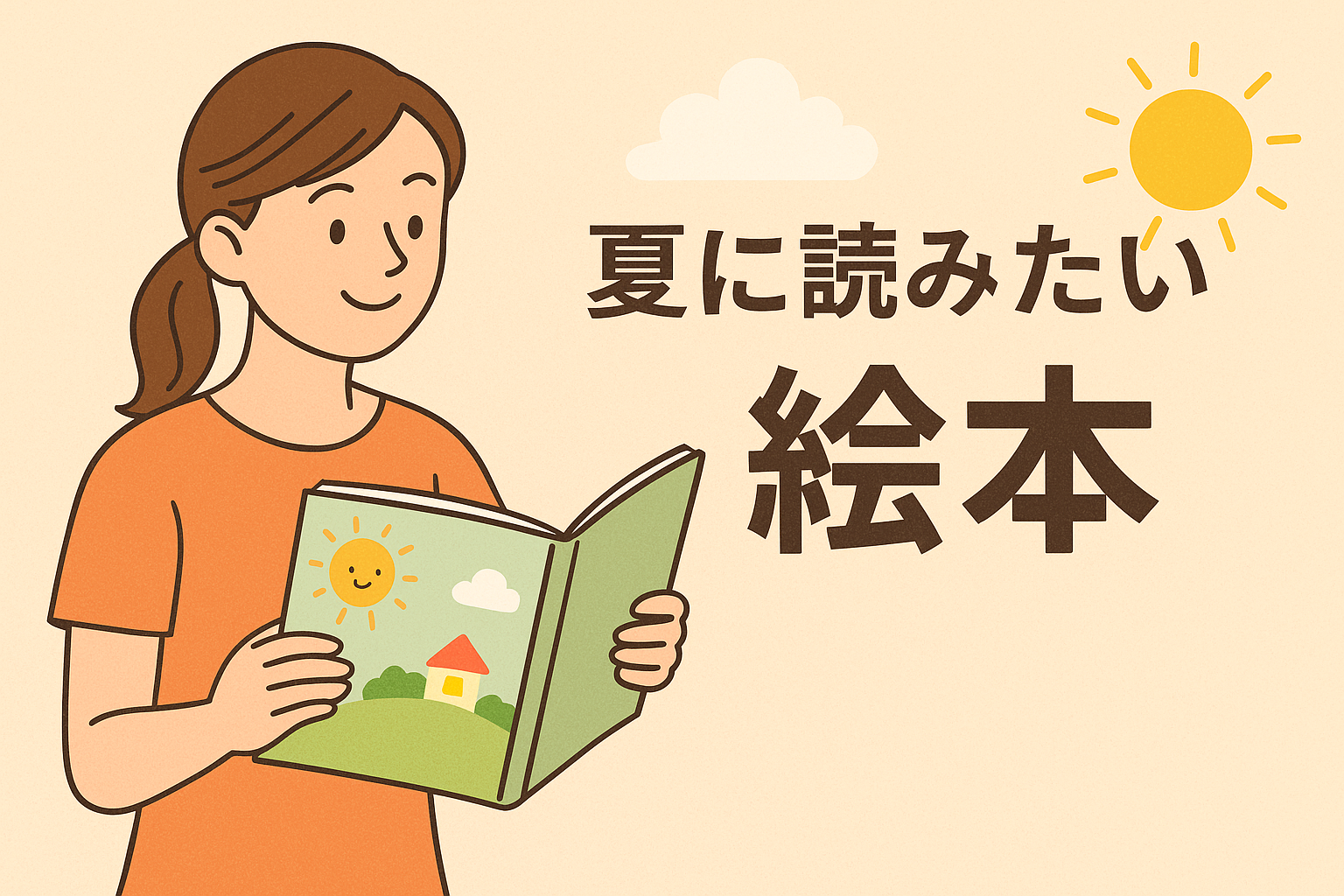
夏ならではの体験を絵本で再確認できる
プール遊び、花火、お祭り、虫とり…。子どもたちが夏に体験することを絵本で振り返ることで、記憶が定着し、言葉での表現力が高まります。「あ、これ知ってる!」という気づきが絵本への興味を引き出し、より深い理解にもつながります。また、同じ体験をしていない子どもにとっては、絵本を通じて間接体験ができ、世界を広げるきっかけになります。
暑さで外遊びが難しい時の強い味方
猛暑日や熱中症警戒アラートが出ている日には、室内での活動が中心になります。そんな時でも、絵本を通して自然や季節を感じることができ、室内にいながらも「夏らしさ」を楽しめます。また、読み聞かせの時間は静と動のバランスを取るうえでも有効で、興奮気味の子どもたちの気持ちを落ち着かせる時間にもなります。
感覚と言葉を育てる「季節の絵本」
夏の絵本は、「つめたい」「ぺたぺた」「きらきら」など五感を刺激する言葉が豊富。氷の感触、打ち上げ花火の音、セミの鳴き声といった夏特有の体験を、言葉と絵で再現してくれます。特に3〜5歳児には、絵と一緒にことばの響きを楽しむことで、語彙力や感性が豊かになります。絵本の中で感覚を言葉に置き換える経験は、子どもたちの表現力を育てる土台にもなります。
夏におすすめの絵本5選【年齢別に紹介】
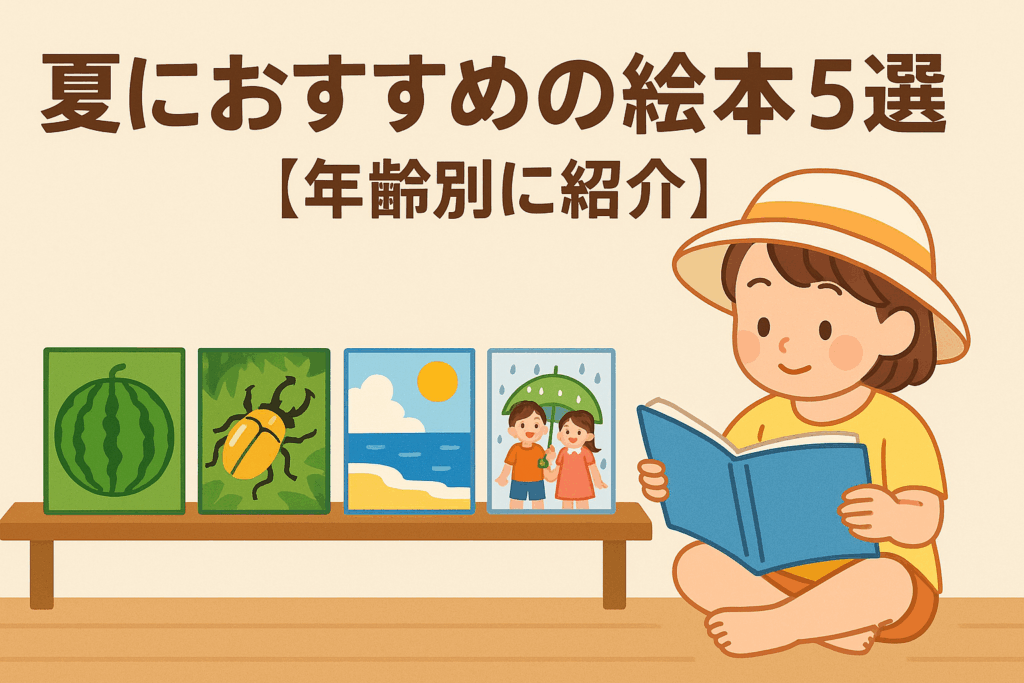
1・2歳児におすすめ『じゃあじゃあびりびり』(まついのりこ/偕成社)
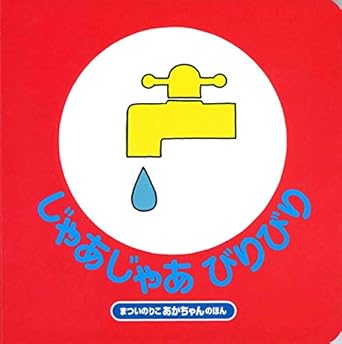
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/614Z0B5LUbL._SY342_.jpg
擬音語たっぷりの絵本は、子どもたちの耳に心地よく、読み聞かせにもぴったり。「じゃあじゃあ」「ぴーぴー」と音を楽しみながら、夏の水遊びを思い出すきっかけにもなります。厚紙でできたボードブックなので、扱いやすく、読み聞かせだけでなく子ども自身が手に取って楽しむのにも最適です。
3歳児におすすめ『きんぎょがにげた』(五味太郎/福音館書店)
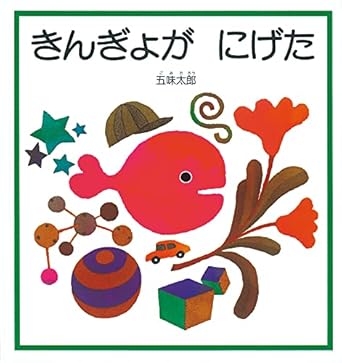
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/61spXMaU9XL._SY342_.jpg
夏の風物詩「金魚すくい」を想起させる絵本。ページごとに逃げた金魚を探す展開が子どもたちに大人気で、集中力と観察力が育ちます。鮮やかな色づかいと、五味太郎さん独特のユーモアある構成が魅力。繰り返し読んでも飽きない、夏に限らず人気の1冊ですが、金魚が登場する季節に合わせて読むとより効果的です。
4歳児におすすめ『なつのいちにち』(はたこうしろう/偕成社)
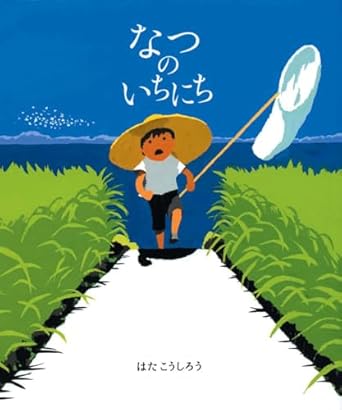
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/61y4O5okzIL._SY385_.jpg
セミの声、汗のにおい、草の感触…。夏の1日を描いたリアルな絵本は、読むだけで夏を感じることができ、五感を使った保育活動とリンクさせやすい1冊です。特にページをめくると現れる「やったー!」の場面は、子どもたちにとって大きなインパクトとなり、感情の共有にもつながります。
5歳児におすすめ『なつのおとずれ』(かがくいひろし/講談社)
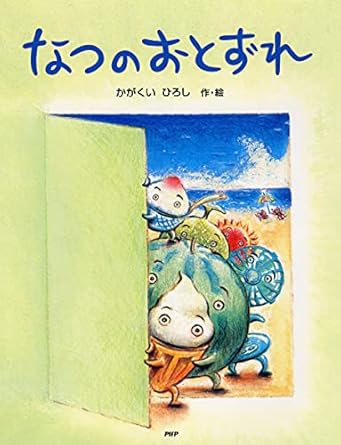
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/91tZ1OnHOLS._SY385_.jpg
ユーモアと情緒が混ざり合う1冊。擬人化された自然たちが夏の訪れを知らせに来る展開で、想像力をかき立てられます。かがくいさんならではのキャラクターの動きや表情が楽しく、読後に子どもたちと一緒に「秋の訪れ」「冬の訪れ」を考える活動にも発展できます。
全年齢で楽しめる『おばけなんてないさ』(せなけいこ/ポプラ社)
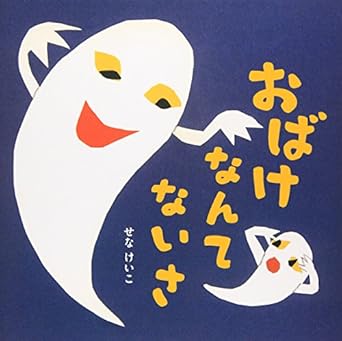
引用:https://m.media-amazon.com/images/I/91J+QpFGdqL._SY342_.jpg
夏といえば“おばけ”も風物詩。ちょっぴり怖くて、でもどこか親しみのあるおばけをテーマにした絵本は、子どもたちの心をくすぐります。歌と一緒に読むと、より楽しい時間に。怖いものを楽しみに変える力、想像と現実のバランス感覚を育てるのに役立ちます。
絵本選びのポイントと読み聞かせのコツ
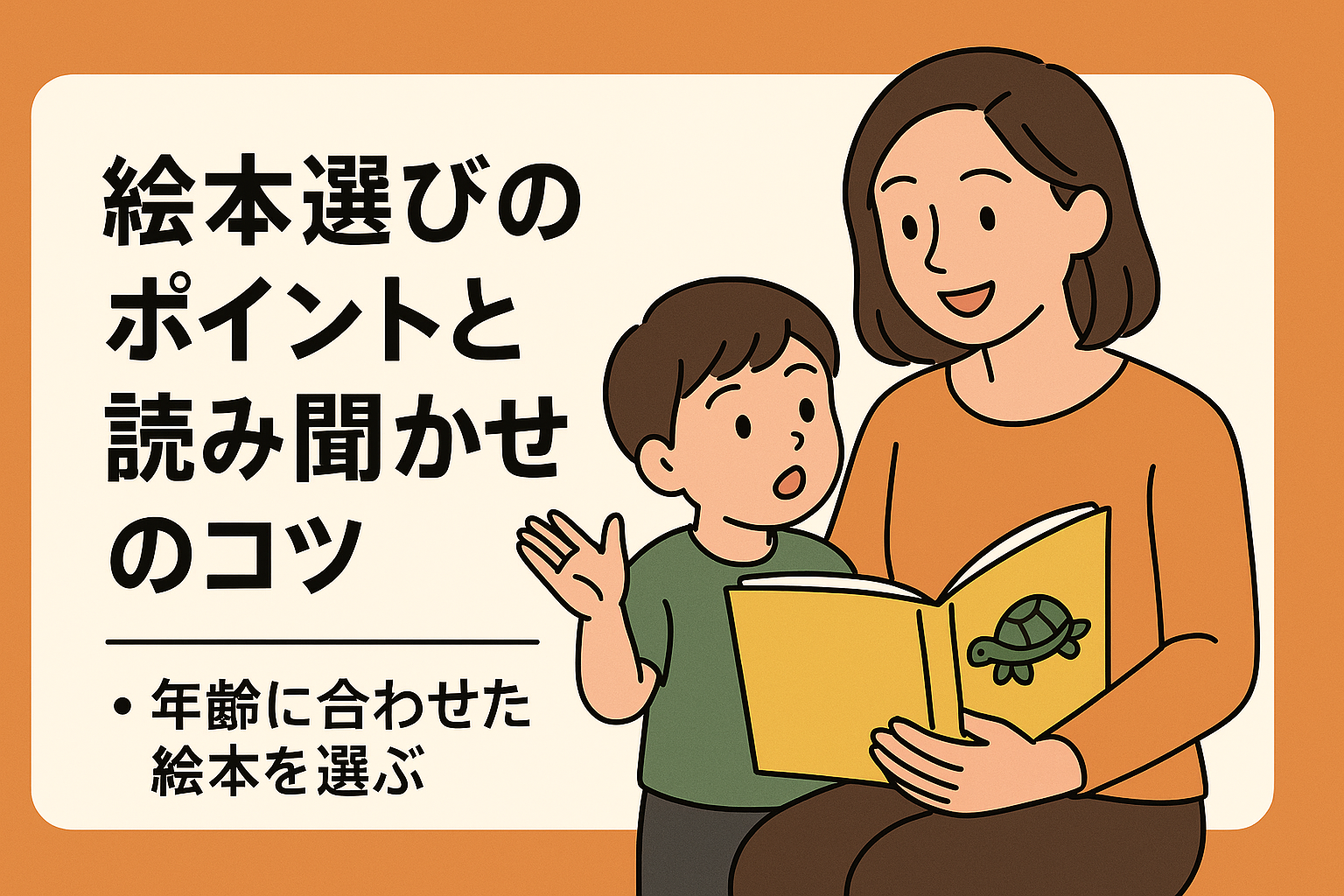
年齢や発達段階に合った内容を
文字数やページ数、ストーリーの展開などは、年齢に応じたものを選ぶことが大切です。1・2歳児には繰り返しが多いものや擬音語が豊富な絵本、3歳以上は少しストーリー性があり、感情移入できる内容が好まれます。子どもたちの発達を意識して絵本を選ぶことで、集中力や理解力を育てることができます。
季節感のあるキーワードが入った絵本を
「なつ」「すいか」「セミ」「あつい」「きらきら」など、季節感のある言葉が入っていると、子どもたちの記憶や経験とつながりやすくなります。園での体験とリンクするキーワードが含まれていると、共感を得やすく、会話のきっかけにもなります。
読み手も一緒に楽しむ姿勢が大切
子どもは大人の表情や声のトーンに敏感です。絵本の世界に入り込みながら、抑揚をつけたり、間を楽しんだりすることで、子どもたちも自然と集中して聞いてくれます。演じるように読む必要はありませんが、物語を一緒に味わう「共感する気持ち」が大切です。読み終わった後の対話も、絵本の魅力をより広げる時間になります。
活動との組み合わせで世界が広がる
絵本の内容と連動した製作遊びや感覚遊びを取り入れることで、絵本の世界がよりリアルになります。たとえば『きんぎょがにげた』を読んだ後に金魚の貼り絵を作ったり、『なつのいちにち』に出てくるセミの鳴き声をまねして遊んだり。絵本が単なる読み物にとどまらず、子どもたちの経験として残るような工夫ができます。
まとめ|絵本で夏をもっと楽しく、豊かに

夏の絵本は、単なる読み物ではなく、子どもの心と体、言葉を育てる貴重な教材です。保育の中で季節感を伝える手段として、ぜひ日々の活動に取り入れてみてください。暑い夏だからこそ、絵本の世界でひんやり・わくわく・キラキラな体験を子どもたちと共有しましょう。
絵本の中には、実際の体験とは異なる世界があります。その「違い」を楽しみながら、「同じだね」「おもしろいね」と語り合える時間が、保育の豊かさを広げてくれます。

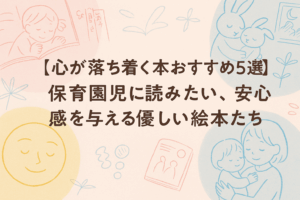
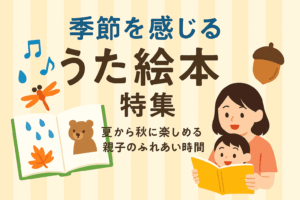
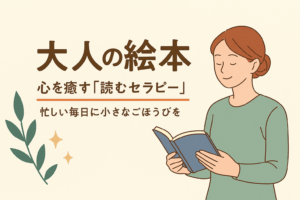



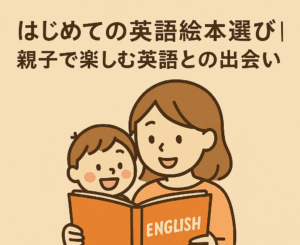

コメント