子どもに人気の絵本シリーズ「ピーマンマン」。
そのインパクトあるネーミングと表紙に、思わず手に取ってみた保育士さんやお母さんも多いのではないでしょうか?
この記事では、「絵本 ピーマンマン」の魅力と活用法について、保育現場での実践例や、家庭での読み聞かせのポイントも交えてご紹介します。
ピーマンマンってどんな絵本?

グリーンマントのピーマンマン (えほん・ドリームランド) [ さくらともこ ]
正義のヒーロー「ピーマンマン」が登場!
「ピーマンマン」は、作・さくらともこ/絵・中村泰敏による絵本シリーズ。
野菜を嫌う子どもたちの前に、突如現れる“ピーマンのヒーロー”が、悪者たち(風邪のばい菌や偏食の敵)をやっつけていくストーリーです。
タイトルからも分かるように、主人公はなんとピーマン。
野菜が主役の絵本としては珍しく、男の子にも人気のある“戦うヒーロー”要素が入っており、野菜嫌い克服を狙えるユニークな作品です。
保育園での読み聞かせにもぴったり!

2歳児〜年長クラスにおすすめの理由
ピーマンマンは、2歳後半〜6歳頃の子どもたちに特にウケが良い絵本です。
正義感に目覚め始めた年齢の子どもたちは、ヒーローが悪者を倒すという構成にワクワク。
また、「ピーマンが苦手…」という子どもたちも、絵本を通してピーマンに親しみを持ち、給食やお弁当に出てきたときにちょっとチャレンジしてみよう、という気持ちが芽生えることも。
食育などの導入に読み聞かせするのもありですね!
ちなみに余談ですが、私が新卒で働いた保育園で2歳児クラスを担任していた時にクラスリーダーの先生がピーマンマンのパネルシアターを持っていて、よく子ども達に見せていました。子ども達は何度見ても毎回釘付けになって見ていた光景は今でも覚えています。(笑)そして、その時に先輩が歌いながらやっていた歌をいまだに私も覚えています。(笑)
読み聞かせのポイント
- ピーマンマンの登場シーンは、声色やテンションを変えて“かっこよく”読むと◎
- 悪者とのやりとりはテンポよく、間を意識して盛り上げる
- 読後には「今日のお昼にピーマン入ってたね」など話題をリンクさせてみるのもおすすめ
子育て中のママにも人気!「家で読んでみたら…」
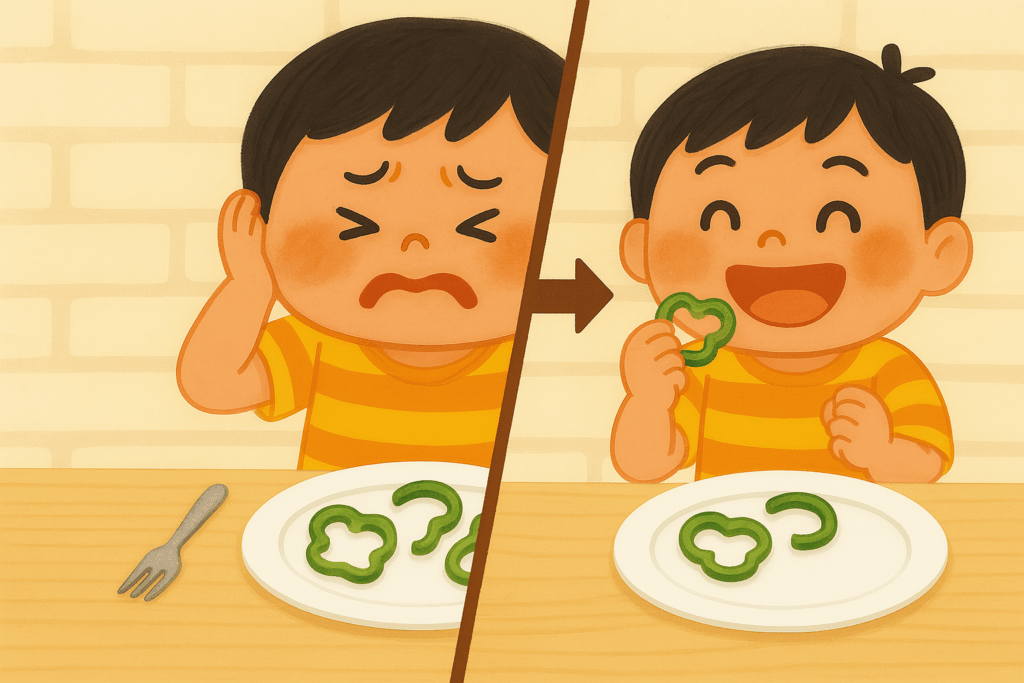
野菜が苦手な我が子に読んでみた
子どもがピーマンを見るだけで「イヤ!」と言う…。
そんなときに出会ったのが「ピーマンマン」だったというママの声もよく耳にします。
実際に読んでみると、
- 「ピーマンマンって強いんだね!」
- 「ぼくもピーマンマンみたいにかっこよくなる!」
という言葉が出てくることも。
子どもにとって、食べ物とヒーローがつながる体験は新鮮で、食への関心や前向きな気持ちにつながります。
絵本をきっかけに親子の会話が増える
読み終わったあと、「じゃあ、ピーマンマンの仲間はどんな野菜かな?」とクイズ形式で遊ぶのも楽しいです。
「ニンジンマン?」「ナスビウーマン?」なんて、子どもと一緒にオリジナルヒーローを考えることで、苦手だった野菜にも自然と目を向けてくれるようになります。
ピーマンマンシリーズには続編も!

実は、「ピーマンマン」にはシリーズ作品が複数あります。
- 『ピーマンマンとかぜひきキン』

ピーマンマンとかぜひきキン (えほん・ハートランド) [ さくらともこ ]
- 『ピーマンマンとよふかし大まおう』

ピーマンマンとよふかし大まおう (えほん・ハートランド) [ 佐倉智子 ]
など、どれも個性的な敵と対決するストーリー。
内容は異なりますが、共通して「ピーマンマンががんばる=子どももがんばろう」と思わせてくれる、前向きでユーモラスな世界観が魅力です。
まとめ|「ピーマンマン 絵本」は読み聞かせにも食育にも◎
「ピーマンマン 絵本」は、読み聞かせで盛り上がるだけでなく、食育や偏食のサポートにも役立つ一冊です。
- 野菜嫌いな子どもも、ヒーロー視点で興味をもつ
- 正義感や想像力を刺激し、楽しい読書体験に
- 親子のコミュニケーションにも自然とつながる
保育園での活動や、おうちでの食事時間をもっと楽しくしたいとき、ぜひ「ピーマンマン」の力を借りてみてくださいね。

グリーンマントのピーマンマン (えほん・ドリームランド) [ さくらともこ ]









コメント