絵本が好きで、その魅力をもっと多くの人に伝えたい——そんな思いを持つ方に注目されているのが「絵本専門士」という資格です。
絵本を通して子どもたちの感性や想像力を育む活動を支える専門家であり、保育・教育・図書館活動などさまざまな分野で活躍できます。
本記事では、絵本専門士とは何か、受講資格、取得までの流れ、活かし方、そして受講を検討する際のポイントを、初めて知った方でも理解できるように解説します。
絵本専門士とは

資格の概要と目的
絵本専門士は、絵本の魅力や可能性を最大限に活かし、幅広い世代に伝えることを目的とした専門資格です。
単なる「絵本好き」ではなく、理論と実践を学び、絵本の持つ文化的価値や教育的効果を広く普及させる役割を担います。
文部科学省が関与する公的性のある資格
この資格は、文部科学省が事業に関与しており、公的性が高いのが特徴です。民間資格とは異なり、全国の図書館・学校・保育施設での認知度も高く、信頼性があります。
絵本文化の普及・発展を担う専門家
絵本専門士は、読み聞かせや講座の実施、選書アドバイスなどを通じて、地域や教育現場における絵本文化の発展に貢献します。資格取得者の多くは、現職の保育士・司書・教員ですが、絵本好きな一般の方も活躍しています。

認定絵本士養成講座テキスト 第2版 [ 絵本専門士委員会 独立行政法人国立青少年教育振興機構 ]
絵本専門士の受講資格と条件
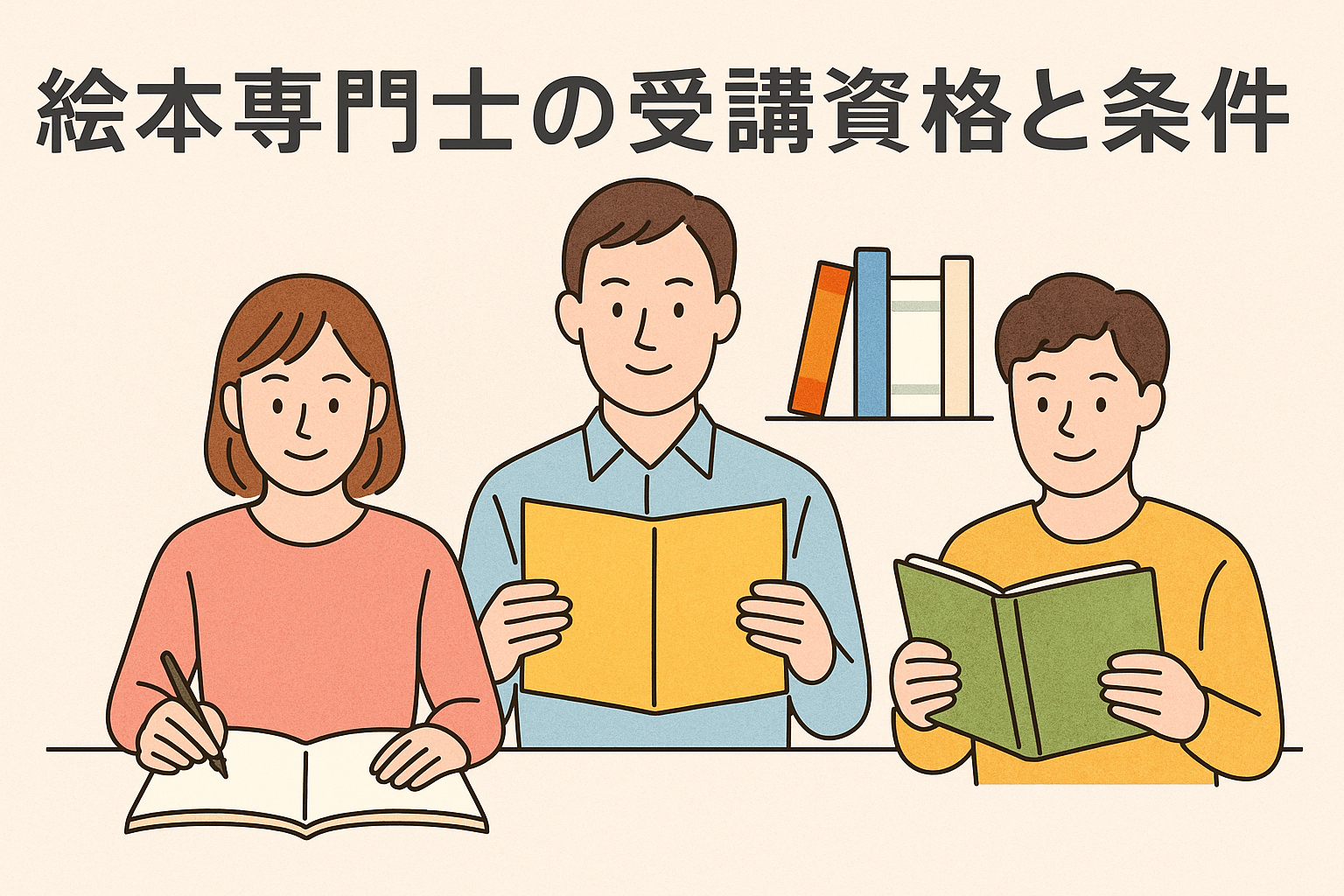
対象となる職種・経験年数
絵本専門士養成講座の受講には、保育・教育・図書館業務など、絵本に関わる実務経験が原則2年以上必要です。
具体的には以下の職種が多く応募しています。
- 保育士・幼稚園教諭
- 小中学校・特別支援学校教員
- 公共図書館司書
- 書店員(児童書担当)
受講に必要な書類や推薦状
受講申込時には履歴書や職務経歴書、推薦状が必要になる場合があります。特に推薦状は勤務先の上司や関係団体からのものが求められ、活動実績や人物像が評価されます。
ちなみに私も今年度(令和7年度)、受験してみました。申し込み時の段階で履歴書などはなかったのですが、ネットでの応募となり、受講動機などを含む小論文(400字程度の内容)をいくつか書きました。
年齢制限や学歴要件はあるのか
年齢や学歴に制限はありませんが、講座の内容は専門的かつ実践的であるため、ある程度の現場経験や絵本に関する基礎知識がある方が望ましいとされています。
絵本専門士養成講座の内容と取得までの流れ
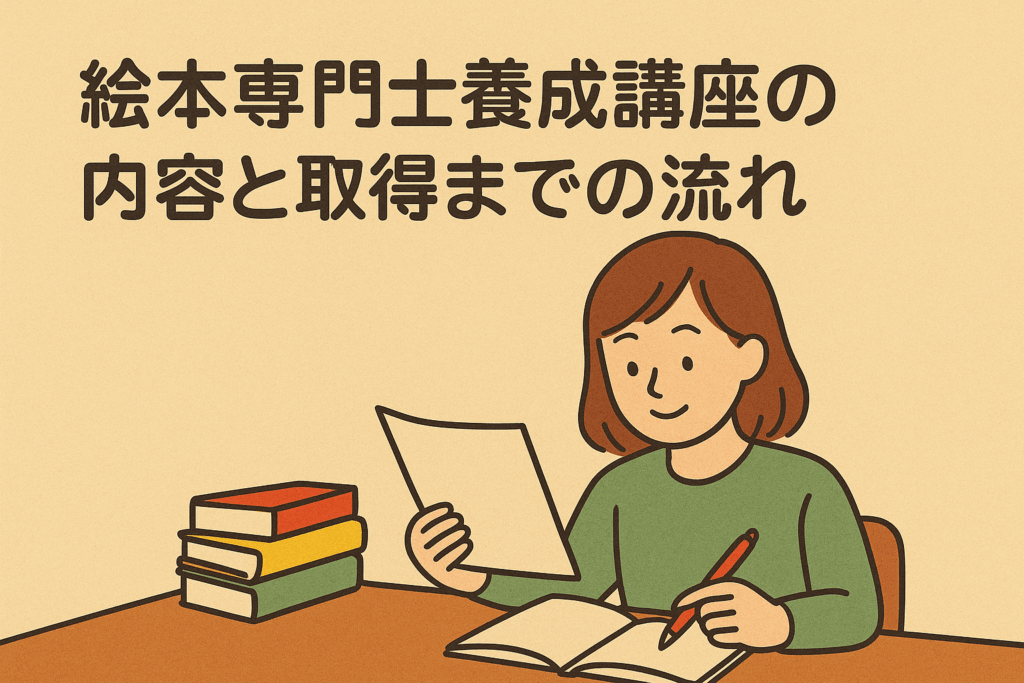
☆ここからは実際に私は受講出来ていないので、調べた内容をもとに説明していきます!↓
講義・演習のカリキュラム例
養成講座では、絵本の歴史・種類・選書方法・読み聞かせ技法などを学びます。加えて、心理学や発達学の視点から絵本を分析する講義もあります。
実際のカリキュラム例:
- 絵本史と児童文学論
- 年齢別の絵本選びと読み聞かせ
- 絵本イベント企画・運営
- 絵本の創作・編集の基礎
課題提出や実地研修の有無
講座中はレポートや課題があり、自分の活動計画を立てて実践報告を行うケースもあります。また、現場での読み聞かせ実習やイベント企画を伴うこともあるそうです。
修了後の認定と資格証の授与
全カリキュラムを修了し、課題を提出すると「絵本専門士」の資格が授与されます。資格証は全国で通用し、名刺や履歴書にも記載できる公式資格として活用できます。
実際に絵本専門士を取得された方の県名や名前は公式HPに記載されています。
詳しくはこちらでご確認を。↓
絵本専門士 | 独立行政法人 国立青少年教育振興機構
絵本専門士の活かし方とメリット
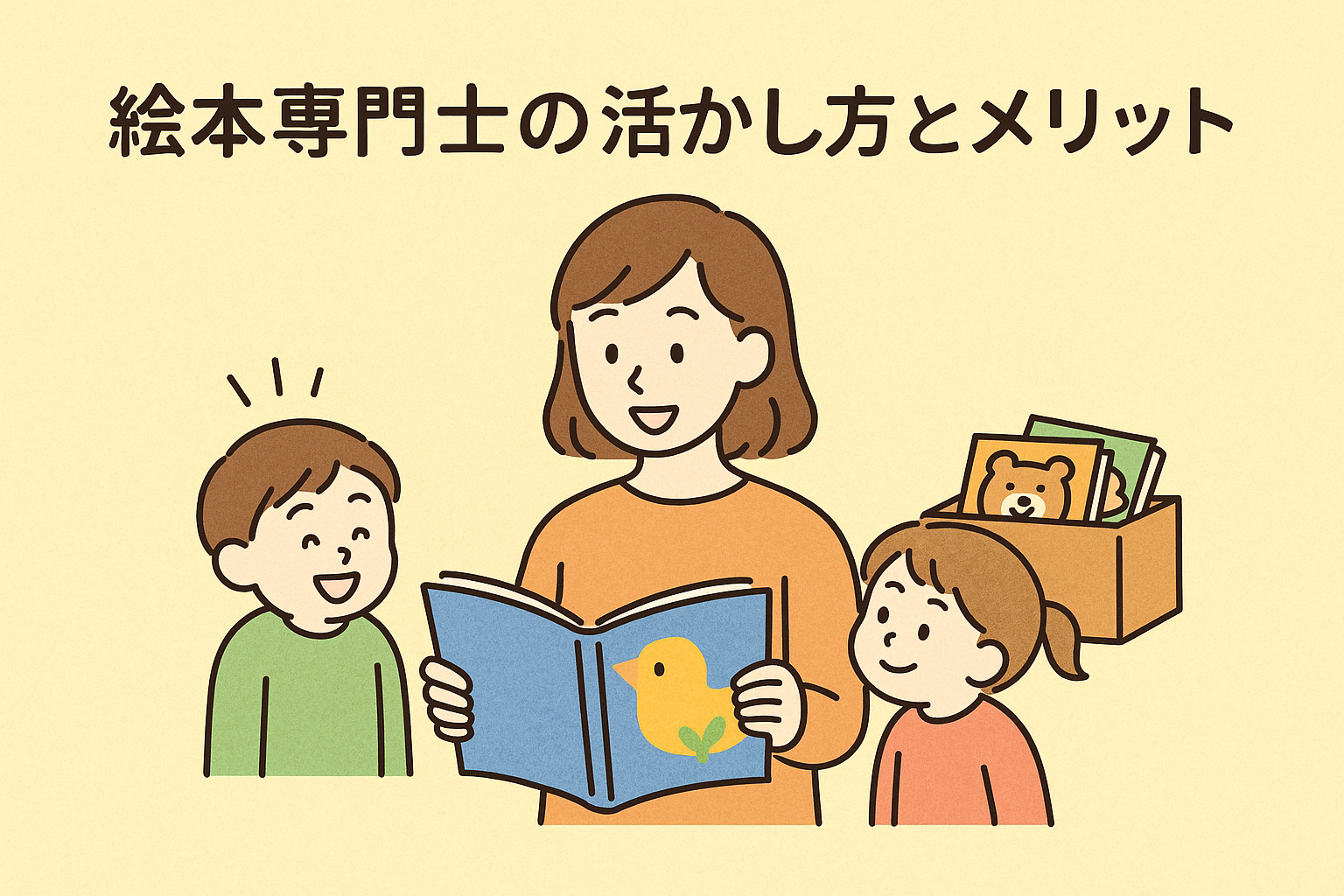
☆実際にこちらの内容も受講者さん達が資格取得後、どのような場面で活躍されているのかをまとめてみました!
意外と身近な所にも、『絵本専門士』さんっているのかも…と思いました。↓
保育・教育現場での活用
資格取得者は、保育園や幼稚園、小学校での読み聞かせ活動や、絵本を活用した授業計画の立案などで活躍しています。子どもたちの読書意欲や表現力を育む役割が期待されます。
図書館・書店・地域活動での活躍例
公共図書館では、おはなし会の企画運営、絵本フェアの選書担当などを任されることもあります。書店では児童書売り場の専門性向上にもつながります。
個人での絵本講座や読み聞かせイベント運営
資格を活かしてフリーランスで絵本講座を開いたり、地域イベントで読み聞かせを行う活動も可能です。SNSやブログでの発信と組み合わせれば、活動の幅はさらに広がります。
絵本専門士になるための準備とポイント
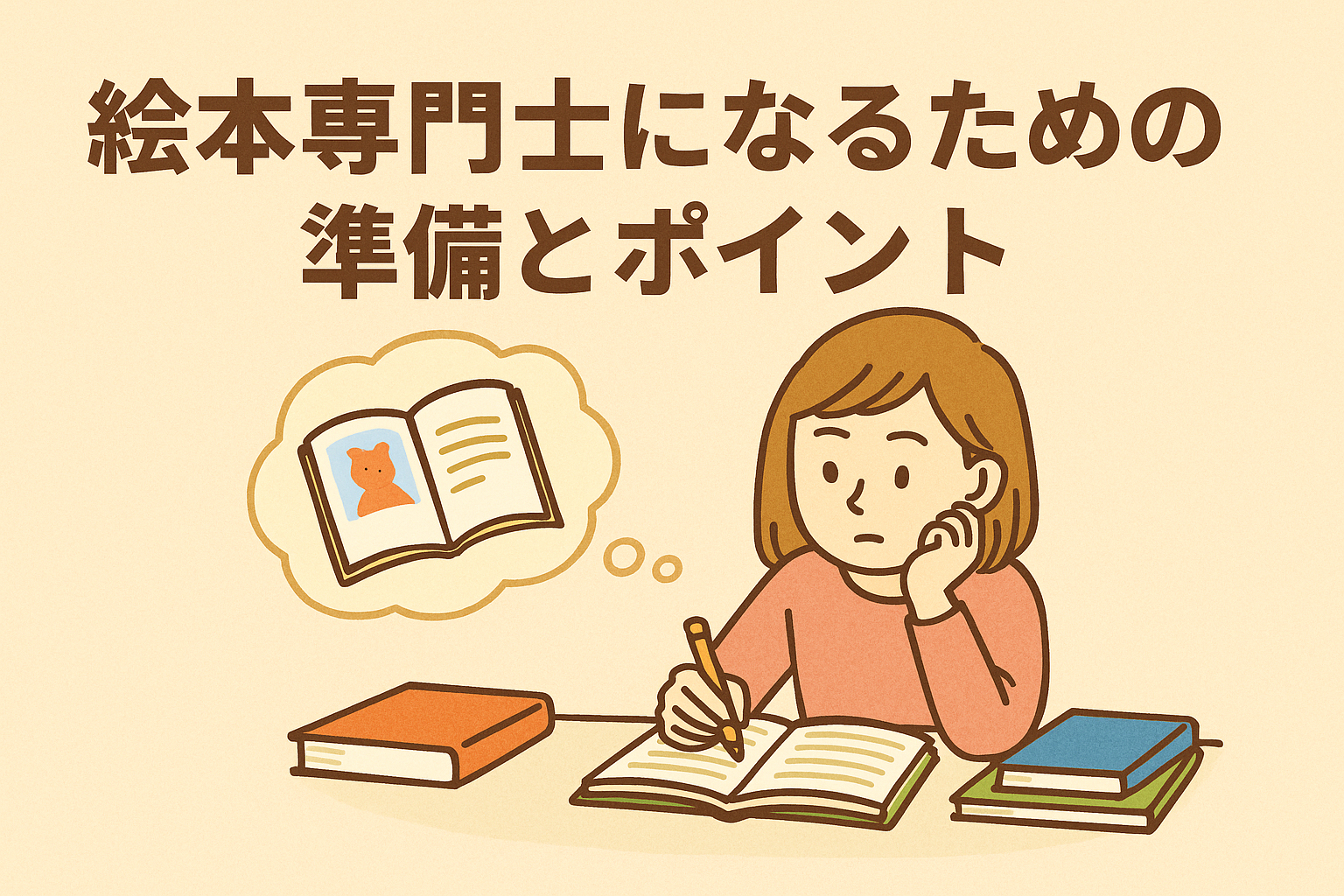
☆実際に私も経験した事を個人的な感想も交えつつ、説明していきます!
選考に通るための志望動機の書き方
応募の際には、なぜ資格を取得したいのか、取得後にどう活動するのかを明確に伝えることが大切です。「地域の子どもたちに絵本の魅力を伝えたい」「保育現場での読み聞かせをより充実させたい」など、具体的な目標を示しましょう。
ちなみに私も取得したい理由や資格を取ったらどのような活動をしたいかは書いたのですが、もっと具体的に書けばよかったのかなと反省した部分でもあるので、自分の思い+読み手の方にも伝わる熱意を示すのがよいのかもしれません。
面接・講義に備えて知っておくべき知識
面接がある場合は、絵本の基礎知識や著名な作家、年齢別のおすすめ絵本などを押さえておくと安心です。また、現場でのエピソードを交えて話せると印象が良くなります。
受講を検討する際の費用・日程・会場情報
費用は数万円〜10万円程度、講座は国立オリンピック記念青少年総合センター(渋谷区代々木)で開催されますが、定員が限られているため早めの申し込みが必要です。受講期間は半年〜1年程度で、仕事との両立を考えて計画しましょう。毎年だいたい6月中旬から翌年1月中旬まで行っています。詳しくはこちら。
↓
https://www.niye.go.jp/wp-content/uploads/2025/02/%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B5%B5%E6%9C%AC%E5%B0%82%E9%96%80%E5%A3%AB%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7%EF%BC%88%E7%AC%AC12%E6%9C%9F%EF%BC%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf
まとめ|絵本専門士は絵本の魅力を広げるスペシャリスト
絵本専門士は、絵本の力を最大限に活かし、地域や教育現場での文化活動を支える専門家です。
保育士や教員、司書などの現職の方はもちろん、絵本好きな一般の方にもチャンスがあります。
「絵本専門士」の資格取得は、絵本を通じて人と人をつなぐ架け橋になる第一歩。興味を持った今こそ、その扉を開いてみてはいかがでしょうか。

認定絵本士養成講座テキスト 第2版 [ 絵本専門士委員会 独立行政法人国立青少年教育振興機構 ]
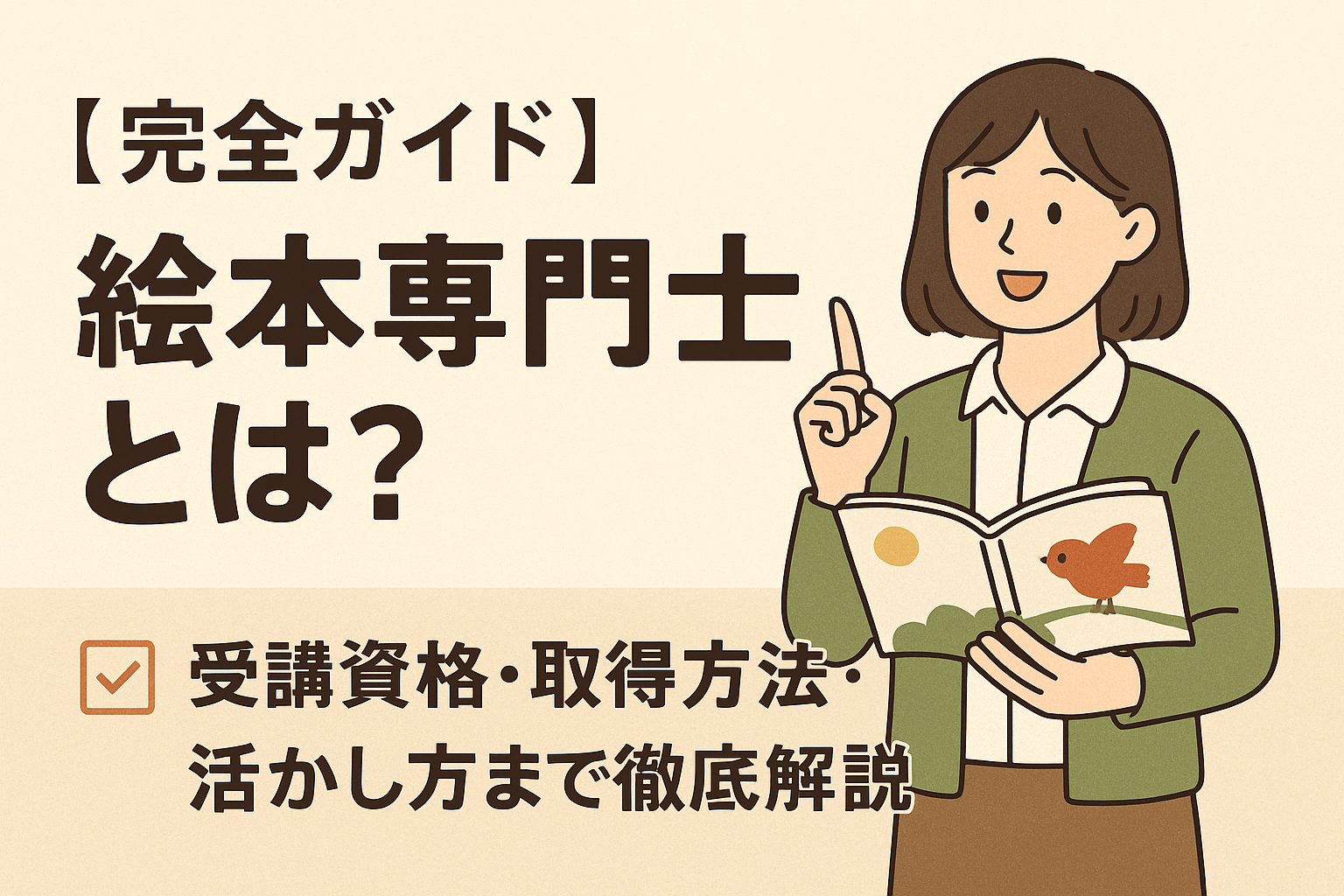
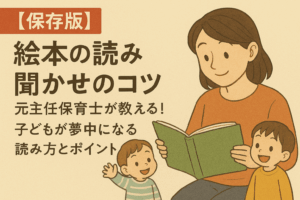

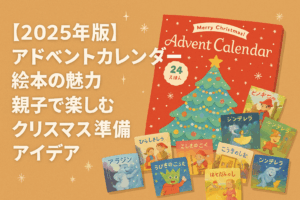
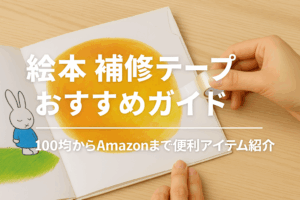
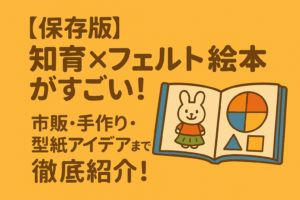



コメント