子どもに初めて読む絵本を選ぶとき、多くの保護者が「やさしい気持ちが育まれる一冊」を探すのではないでしょうか。そんな思いにぴったりなのが、 香山美子作・柿本幸造絵の『どうぞのいす』 です。
シンプルながらも温かいストーリーで、世代を超えて読み継がれている名作絵本。今回は、そのあらすじや読み聞かせのポイント、子どもへの効果などを詳しくご紹介します。

「どうぞのいす」のあらすじ

【送料無料】どうぞのいす/香山美子/柿本幸造/子供/絵本
ある日、うさぎさんが小さな椅子をつくります。森の動物たちのために「どうぞのいす」と名前をつけて、木の下に置きました。
そこへ、最初にやってきたのは ろばさん。どんぐりをたくさん持っていて、休憩がてら椅子に座り、どんぐりを置いて立ち去ります。
次にやってきたのは くまさん。どんぐりを見て、「どうぞなら遠慮なく」と食べてしまいます。でも、「なくなっては悪い」と、自分が持っていた蜂蜜を椅子の上に置いていきました。
その後も、きつねさんがパンを、りすさんがくりを…というように、椅子の上の食べ物はどんどん入れ替わっていきます。最後に戻ってきたろばさんは、自分が置いたどんぐりの代わりにおいしいくりを見つけて、大喜び。
この絵本は、動物たちが「どうぞ」の気持ちで自然に分け合い、思いやりの連鎖が広がっていく物語です。
絵本の魅力
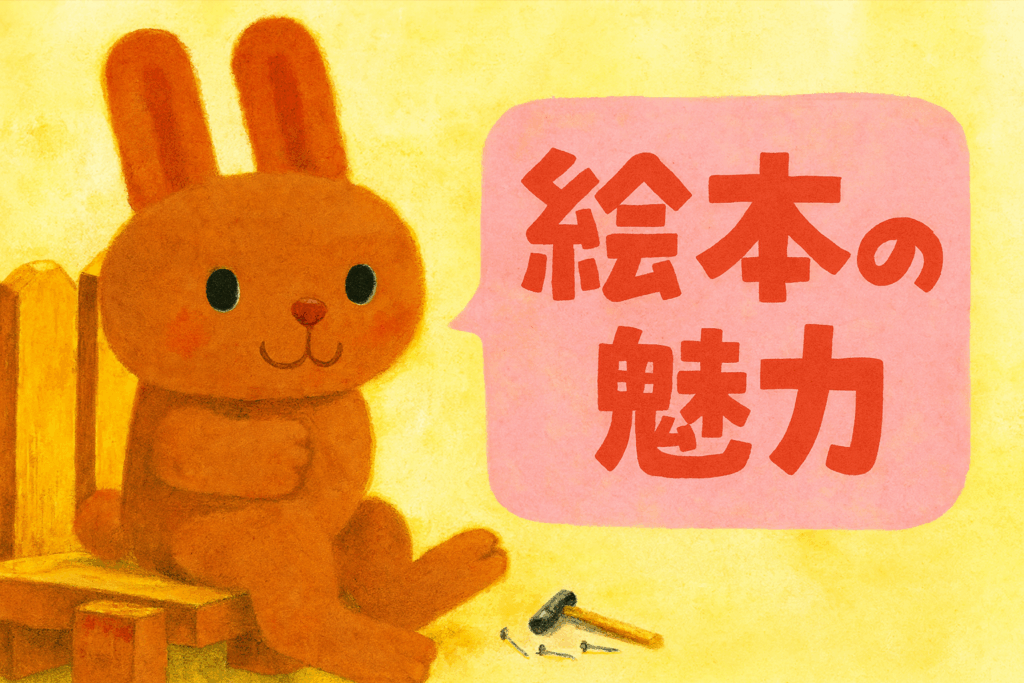
1. 思いやりの心を育む
「どうぞ」という言葉が繰り返し登場し、子どもは自然に「分け合うことの楽しさ」を感じられます。やさしさがリレーのようにつながる展開は、小さな読者にも理解しやすいでしょう。
2歳後半くらいになってくるとこの話のストーリーを理解してくれるようになり、ちょっとしたやりとりの中でも「どうぞ!」と子どもが譲ってくれる場面が増えました!
2. 繰り返しが楽しいストーリー
動物たちが次々に登場し、食べ物を置き換えていくパターンは、子どもが予想を立てながら楽しめる仕組みになっています。「次は誰が来るのかな?」とワクワク感が続きます。
次はどの動物が登場するのか、お気に入りの動物がいるのか読み聞かせをしていた時は子ども達もそわそわしていました。(笑)出てきた瞬間、「わー!」と盛り上がった事もありましたよ。
3. 温かみのあるイラスト
柿本幸造さんのやわらかなタッチは、動物たちの表情や森の雰囲気を優しく描き出し、読み聞かせをより心地よい時間にしてくれます。
個人的にとっても絵のタッチが好きです。見ていてほっこりしちゃうんですよね。
読み聞かせのポイント

- 「どうぞ」の部分を強調して読む
繰り返されるフレーズをゆっくり、少し声色を変えて読むと、子どもが自然と一緒に言いたくなります。 - 動物ごとの声を演じ分ける
くまさんは太く低め、りすさんは軽やかに…と変化をつけることで、物語に引き込まれます。 - ページをめくる前に「次は誰が来るかな?」と問いかける
子どもの予想力や想像力を引き出す読み方ができます。
子どもへの効果

- 思いやり・やさしさの芽生え
「自分だけのもの」から「誰かと分け合う楽しさ」へと気持ちが広がります。 - 言葉のリズム感が育つ
繰り返しの多いストーリーで、ことば遊びのように楽しめます。 - 安心感を与える
トラブルが起きず、やさしいやりとりで物語が進むため、寝る前の読み聞かせにもおすすめです。
「どうぞのいす」が人気の理由
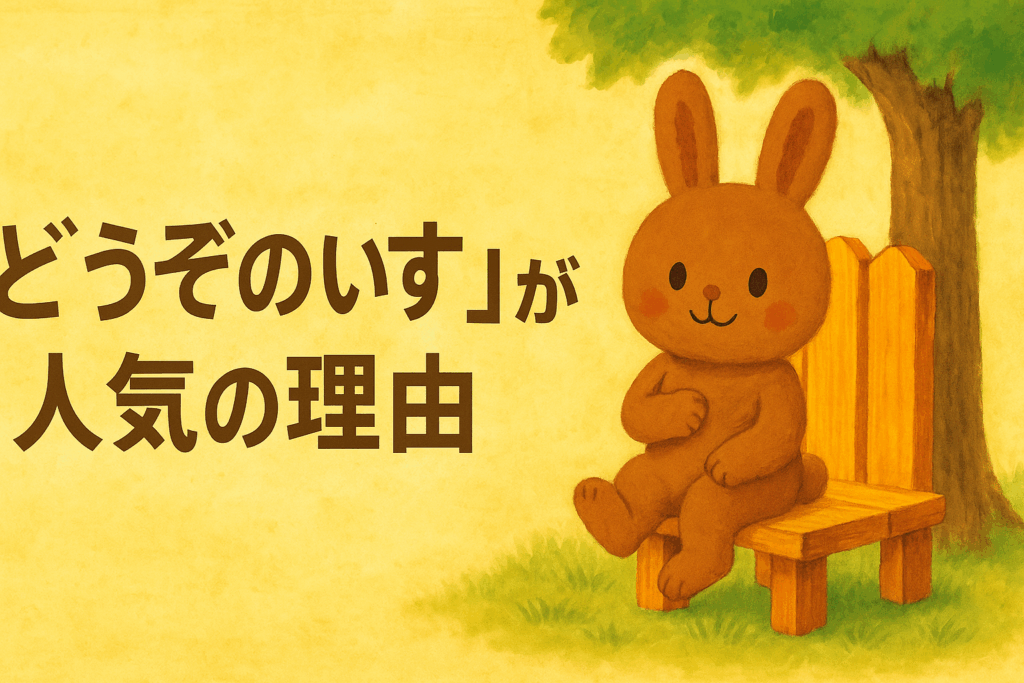
出版から長い年月が経っても売れ続けているのは、単なる物語以上に 普遍的なメッセージ が込められているからです。
社会生活の基盤である「分け合い」「思いやり」が自然に伝わるこの絵本は、親子の時間をあたたかく彩ってくれます。
ちなみに余談ですが、私もこの絵本は保育をしていたお友達からプレゼントでもらいました。
自分ひとりで読むのと、子ども達に読み聞かせとして読むのはまったく違うけれど、どちらも心温まることには変わりないです。それもベストセラーと言われる特徴なのかなと感じました!
まとめ
『どうぞのいす』は、シンプルで優しいストーリーながら、読む人の心に深く残る名作です。
あらすじを知っている人も、読み聞かせであらためて子どもの反応を感じると、その魅力を再発見できるでしょう。
ぜひこの秋、親子の読書時間に取り入れてみてください。きっと「どうぞ」の気持ちが家庭の中でも広がっていきますよ。

【送料無料】どうぞのいす/香山美子/柿本幸造/子供/絵本









コメント