子どもたちの間で長く愛されている『おばけなんてないさ』。
タイトルを聞くだけで、あのメロディが頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか。
もともとは童謡として生まれ、今では絵本としても人気を集めています。
夜やおばけを怖がる子どもたちに、「怖いものは本当にあるのかな?」と問いかけながら、
優しく勇気づけてくれる1冊です。
この記事では、『おばけなんてないさ』のあらすじや対象年齢、歌との関係、
そして読み聞かせのポイントをわかりやすく紹介します。
『おばけなんてないさ』ってどんな絵本?

【送料無料】おばけなんてないさ/せなけいこ/槙みのり
歌から生まれた人気の絵本シリーズ
『おばけなんてないさ』は、童謡として誕生した作品をもとに作られた絵本です。
作詞は「せなけいこ」さん、作曲は「峯 陽(みね よう)」さんによるもので、
1969年の発表以来、今も保育園や幼稚園で歌い継がれている名曲です。
その後、絵本版として刊行されたことで、
「歌だけでなく、絵で楽しめるおばけの世界」として再び注目されました。
夜やおばけが怖いと感じる子どもでも、
この絵本を通じて“怖いけどちょっと楽しい”感覚を味わえるのが魅力です。
あらすじ|夜の中で出会う“ちょっとこわくてかわいい”おばけたち
夜の静かな時間、子どもが「おばけなんてないさ」と口ずさみながらも、
頭の中ではおばけのことを考えています。
「ほんとに出るかもしれない…」「でもいないよね」と、
怖い気持ちと好奇心の間を行ったり来たり。
ページをめくるごとに、
白くてふんわりしたおばけたちが登場しますが、
どれもどこか愛嬌があり、決して怖くはありません。
むしろ、おばけのほうが子どもたちに興味津々といった様子で、
「ぼくたちも一緒にあそびたいな」と言っているように見えます。
最後には「おばけなんてうそさ」と言いながらも、
心のどこかで“やっぱりいるかも”と感じさせる結末。
この余韻が、子どもたちの想像力をぐっと広げてくれるのです。
登場するおばけたちのキャラクター紹介
絵本に登場するおばけたちは、どれも個性豊かでユーモラス。
白いシーツをかぶったような姿や、
ふわふわと浮かんで笑っているおばけ、
びっくりして目を丸くするおばけなど、
ページごとに少しずつ違う表情を見せます。
特に小さな子どもにとって、怖いよりも「かわいい」「面白い」と感じられるデザインです。
絵を見ながら「このおばけは笑ってるね」「どこに行くのかな?」などと会話をしながら読むと、
より楽しめます。
☆私も保育園に新卒で入りたての頃は少し苦手だったのですが、年数を重ねていくうちに愛着がわいてきてお気に入りの絵本シリーズになりました!
対象年齢とおすすめの読み聞かせシーン
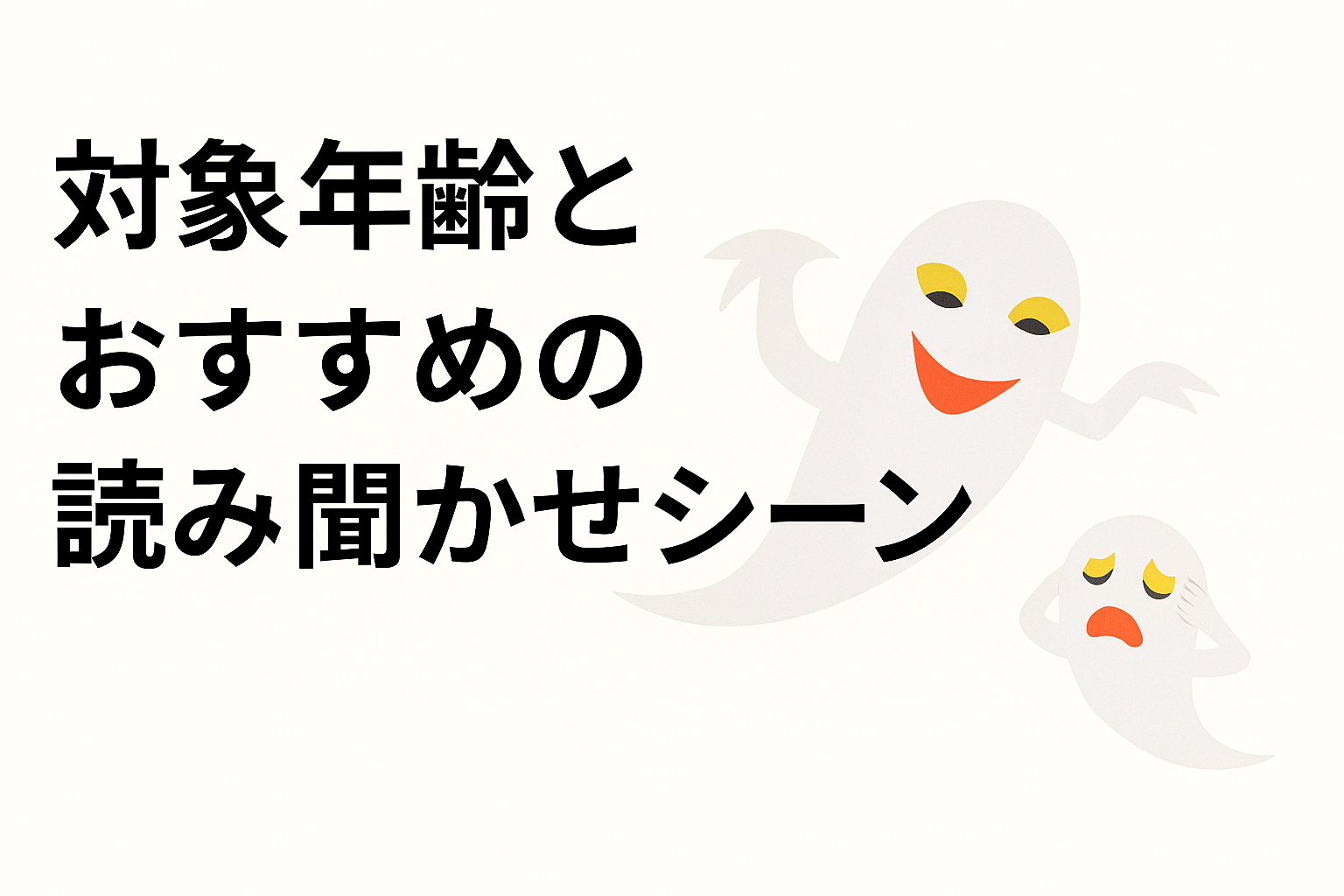
対象年齢は?はじめての“こわい”を楽しめる時期
『おばけなんてないさ』の対象年齢は、3歳ごろからが目安です。ですが、保育園では1歳児から読んでも大丈夫!
☆ちなみに私が1歳児で担任していた頃のMちゃんはこの絵本が大好きで、入園したての頃に泣いていてもこの絵本の歌を歌うと泣き止んでいたのを今でも覚えています!
内容や言葉がやさしく、リズミカルな繰り返し表現が多いので、
小さな子どもでも理解しやすく、歌と合わせて覚えやすい構成になっています。
また、夜やおばけに興味を持ち始める時期でもあり、
「こわい」と「たのしい」が混ざった感情を学ぶ良いきっかけにもなります。
保育園・家庭での読み聞かせタイミング
保育園では、夕方の帰りの会やお昼寝前の時間に読むと効果的です。
「おばけ」というテーマが夜を連想させるため、
おやすみ前の絵本タイムにもぴったり。
家庭では、寝る前にライトを少し落として、
優しく歌を口ずさみながら読むと雰囲気が出ます。
怖がりな子でも、親が一緒に歌ってくれることで安心感を得られます。
怖がりな子にもおすすめできる理由
絵本の中に登場するおばけたちは、どれも怖くないおばけばかり。
「おばけ=怖い存在」ではなく、
「ちょっと不思議で、話しかけてみたい存在」として描かれています。
そのため、怖がりな子どもでも楽しみながら読めるのがポイント。
また、「おばけなんてないさ、でもちょっといるかも」というあいまいな世界観が、
子どもの想像力を刺激します。
怖い気持ちを無理に否定せず、
「怖いけど、そんな自分も大丈夫」と思える気持ちの成長をサポートしてくれる絵本です。
☆この時に注意するべき事は決して怖がらせないこと。保育士や大人がわざと怖がらせてしまうと子どもは怖い印象を持ち続けてしまうので、気をつけましょうね!
歌と一緒に楽しむ『おばけなんてないさ』
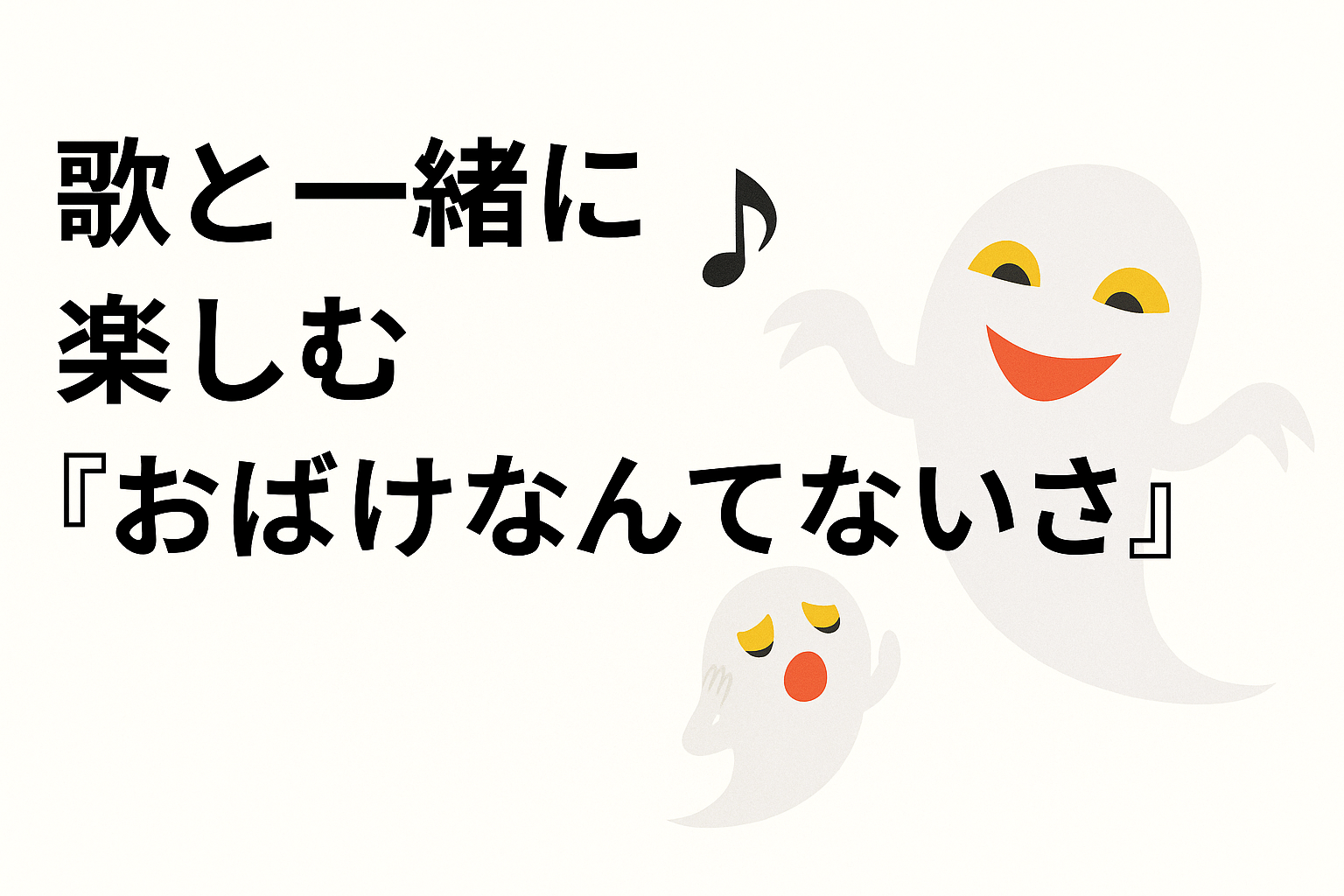
もとは童謡として親しまれた人気曲
この作品は、童謡『おばけなんてないさ』として1960年代に発表されました。
明るいメロディにのせて、「おばけなんてうそさ」と繰り返す歌詞が特徴です。
多くの保育園・幼稚園で歌われており、
世代を超えて親子で一緒に口ずさめる名曲でもあります。
絵本版は、この歌詞をもとに構成されており、
歌詞の世界がページごとに絵で表現されています。
そのため、歌いながら読むことで、より臨場感が増すのです。
歌詞のメッセージに込められた“勇気”と“安心”
歌の中で繰り返される「おばけなんてないさ、でもちょっとあるかもね」という言葉。
実はこのフレーズに、子どもの心の揺れが込められています。
「怖い気持ちをなくそう」と頑張るけれど、
「やっぱり怖い…」という本音もちゃんと受け止めてくれる。
その優しさこそが、この作品が長く愛されている理由です。
読み聞かせに歌を取り入れるときのコツ
絵本を読むとき、途中でリズミカルに歌を混ぜるのもおすすめです。
声のトーンを変えたり、テンポをゆっくりにしたりすることで、
子どもが物語の世界に引き込まれます。
保育園では、ピアノや鈴などを使って歌いながら読むと、
自然とみんなが笑顔になるはずです。

蛍光カラーパネルシアター おばけなんてないさ
イラストの魅力と絵本ならではの表現

かわいらしいおばけたちのタッチと色使い
イラストは、夜の静けさの中にも温かみが感じられる柔らかなタッチ。
おばけの白と背景の濃紺が対比されていて、
ページを開くたびにふんわりと幻想的な雰囲気が広がります。
小さな子どもにもわかりやすい構図で、
シンプルながら印象に残るデザインです。
ページごとの光と影の演出が楽しい
暗闇の中で光る窓、月の明かりに照らされた道、
おばけのまわりにぼんやりと浮かぶ光の輪…。
そんな光と影のコントラストが、怖さとやさしさを同時に感じさせてくれます。
読むたびに新しい発見があるので、
繰り返し楽しめるのもこの絵本の魅力です。
子どもが「まねっこしたくなる」表情と動き
おばけたちが歌いながら動いているような描写が多く、
子どもがまねをしたくなるようなポーズがいっぱい。
「おばけなんてないさ〜♪」と手を広げて歌う子の姿が目に浮かびます。
絵と歌、両方のリズムを感じられる構成なので、
読み聞かせと体あそびを組み合わせても楽しいでしょう。
『おばけなんてないさ』をもっと楽しむアイデア

手作りおばけであそぼう|製作あそびに発展
絵本を読んだあと、白いティッシュや紙コップで“おばけ作り”をしてみましょう。
糸で吊るして風にゆらすだけでも、子どもたちは大喜び。
自分で作ったおばけと一緒に歌えば、絵本の世界がさらに広がります。
☆また、ハロウィンイベントがある10月の製作にもぴったりですよ!
夜の絵本タイムにおすすめの演出
お部屋の明かりを少し暗くして、懐中電灯でページを照らしながら読むと、
まるでおばけが動き出すようなワクワク感に。
親子で「おばけいるかな?」と話しながら読むと、
怖い気持ちが笑いに変わっていきます。
似たテーマで楽しめる“おばけ絵本”のおすすめ
- 『ねないこだれだ』(せなけいこ/福音館書店)

【送料無料】ねないこだれだ/せなけいこ/子供/絵本
- 『おばけのてんぷら』(せなけいこ/ポプラ社)

【送料無料】おばけのてんぷら/せなけいこ
- 『おばけパーティー』(ジャック・デュケノワ/ほるぷ出版)

【送料無料】おばけパーティ/ジャック・デュケノワ/大澤晶
どれも「怖いけどかわいい」おばけが登場する人気作。
『おばけなんてないさ』とあわせて読むと、
おばけの世界がもっと好きになるでしょう。
☆どれも私にとってお気に入りの絵本たちなので、ぜひ一度手にして読んでもらえたら嬉しいです!
まとめ|歌と絵本で“おばけ”を怖くない存在に
『おばけなんてないさ』は、
怖いものをただ「怖くないよ」と言い聞かせるのではなく、
「怖いけど、笑っちゃう」「怖いけど大丈夫」と、
子どもの心に寄り添う絵本です。
歌と一緒に読むことで、親子の距離もぐっと近づきます。
ぜひ、おうちや保育園で“こわくないおばけ”の世界を楽しんでみてください。
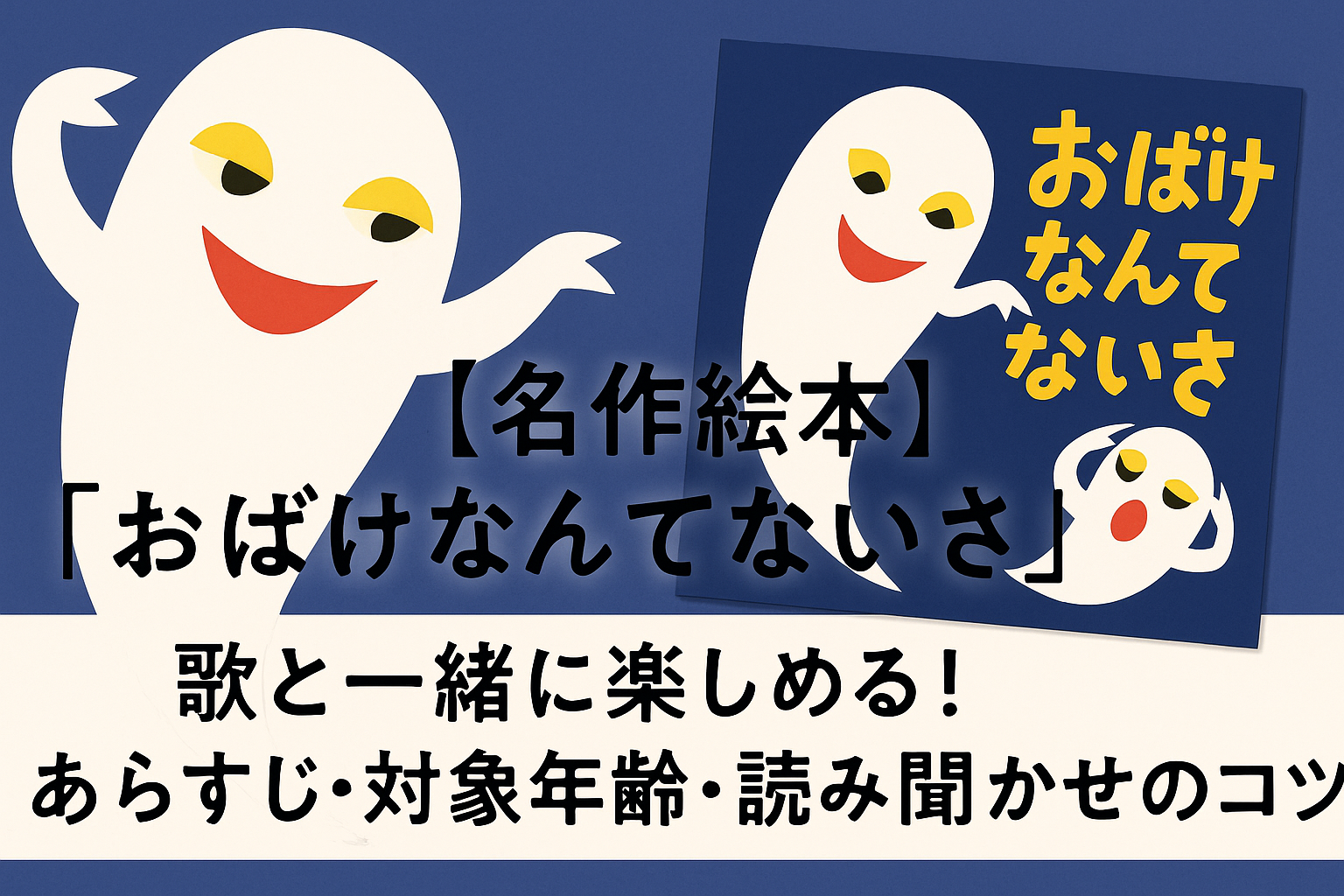








コメント